第6回 日本木青連綱領 半世紀を超えて息づく言葉
こんにちは。日本木材青壮年団体連合会(日本木青連)会長の長谷川泰治です。会長コラム「木力NOTE」第6回では、日本木青連の原点ともいえる日本木青連綱領をご紹介します。この綱領には、私たちが活動を進めるうえでの指針と、歴代の先輩方が脈々と受け継いできた思いが込められています。なお、第5回で取り上げた会歌と同じく、今回の執筆にあたっても“ミスター木青連”こと瓦野光貴君(現・和歌山会団所属)から貴重な歴史やエピソードを教えていただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
日本木青連綱領は、活動の方向性と精神を示す大切な拠り所であり、理事会や式典の冒頭では会歌とともに今も唱和されています。先日、ある若手会員からこんな質問を受けました。
「会団の活動において、何を考え、どう行動すべきでしょうか。」
私は迷わずこう答えました。
「綱領を読んでほしい。綱領こそ、我々の活動の指針だから。」
後で聞いたところ、彼は同じ質問を歴代会長にもしていたそうで、返ってきた答えは私と同じだったそうです。誰かに教えられたわけではなくとも、日本木青連での活動を重ねる中で、私自身、何度も綱領に立ち返り、行動や判断の軸としてきました。日本木青連綱領は、それほど私たちにとって確かな力を持っています。

<各地の理事会、式典で会旗とともに日本木青連綱領が掲げられます>
では、この綱領はどのようにして生まれたのでしょうか。
日本木青連の前身である全国林材青壮年団体連合会(略称:林青連)は、昭和31年(1956年)10月13日、全国から54会団・177名の有志が東京・銀座の紙パルプ会館に集い、創立総会を開催して発足しました。初代運営委員長(第1代会長)は伊藤一郎先輩で、創立時には次のような力強い宣言が掲げられました。
「今日、林材界が当面する課題は、青壮年層においても看過できるものではなく、そのため積極的に対処していく機運が全国各地に盛り上がっております。業界の実務の第一線に立ち、またこれから第一線に立たんとする青壮年層は、この中で全国各団体を網羅し、本連合会を結成いたしました。親睦と交流を通じ相互の啓発を目指して結ばれた全国林材青壮年団体連合会は、未だ加入をみない団体を迎え入れ、発展強化を図り、業界振興の担い手となるべく努力するものであります。」
その後、昭和42年(1967年)に執行部がこの創立宣言に基づき綱領の原案を作成し、昭和43年(1968年)には運営委員会の決定により塚本委員長を中心とした「綱領委員会」が設置されました。4月13日に東京で綱領委員会が開かれ、翌14日の運営委員会で承認、4月22日には榎戸運営委員長の名で各会団に報告され、6月14日の通常総会にて正式に決定されました。こうして「林青連綱領」が樹立されました。ちなみに、第10代榎戸会長までは、会長のことを運営委員長と呼んでいたそうです。
綱領は、会員の意思統一を図り、最大多数の共感と支持を得るために必要とされました。当時は役員に45歳の年齢制限があり、活動できる分野にも制約があったため、「会員企業の繁栄があってこそ林青連の活動は意味を持つ」という考え方が重要視されました。討議では、会員個人と林青連の関係、全木連と林青連の関係、地域業界との関係、林青連はなぜ存在するのか、そして業界の将来と林青連の位置づけといった論点が挙げられ、将来を見据えた組織の理念が形作られていきました。
昭和48年(1973年)に林青連から木青連へと名称変更を経て、今日の日本木青連に受け継がれる綱領は、今も変わらず私たちの活動の根幹にあります。
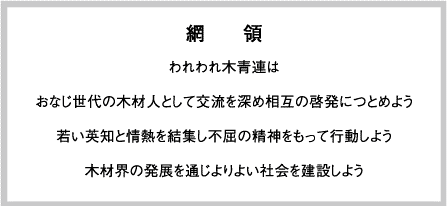
これが、日本木青連の綱領です。
この短くも力強い言葉には、世代を超えて共有できる価値観が込められています。交流はただの親睦ではなく、新しい発想と気づきを呼び起こす場です。若い英知と情熱は、机上の理屈を超え、行動に移す力となります。そして木材界の発展は、単に業界の繁栄を意味するのではなく、暮らしや街、そして未来の社会を形づくることに直結しています。
価値観も、技術も、人のつながり方も時代とともに変わっていきます。しかし、私たちが大切にすべき理念は変わりません。綱領は額に飾っておくだけのものではなく、現場で汗を流すとき、仲間と向き合うとき、新たな挑戦に踏み出すとき、その行動の中で生きてこそ意味があります。これからも日本木青連は、この綱領のもとで力を結集し、実行と成果によって木材業界と社会の未来をつくっていきます。
綱領に先立ち昭和41年に作られたのが、日本木青連のロゴマークです。3本の木と木材の「M」、青壮年の「S」、そして連合会の「R」の文字が入ったロゴマークは、会員からデザインを募集し、集まった23点から、名古屋木材青壮年会の安藤友一歴代会長の作品に決定しました。このロゴマークも、現在、会員バッジ、会旗の他、様々な場所で使われています。

<木青連バッジは今期から木製になりました>

コメントをお書きください
小日向 直人 (火曜日, 09 9月 2025 15:29)
OBは、木青連の木製バッジはどこで購入できるのでしょうか?